
トレザーが問い続ける「真の所有」とは
暗号資産ハードウェアウォレットのパイオニア企業トレザー(Trezor)。同社が本社を置くチェコ共和国プラハで、先月製品発表イベント「Trezor TBD—Trustless by Design—」が開催された。
イベントでは、最新のハードウェアウォレット「Trezor Safe 7」が発表され、プラハがビットコイン文化の中心地として発展してきた背景や、自分の資産を自身で守るというトレザーの精神をテーマにした複数のセッションが行われた。また、トレザー製品のハンズオンや、透明性を重視する開発姿勢に焦点を当てたワークショップも実施され、世界中から集まった暗号資産愛好家や開発者で会場は熱気に包まれた。
今回、あたらしい経済編集部はトレザーのCEOマチェイ・ザーク(Matej Zak)氏にインタビューを実施。セルフカストディの意義、オープンソースへのこだわり、そして暗号資産業界における自由と規制のバランスについてなど語っていただいた。
 Matej Zak氏
Matej Zak氏高まる自主管理意識とセルフカストディの現在地
── マチェイさんの視点から見て、ハードウェアウォレット市場はどのように変化してきたと感じていますか? また、ハードウェアウォレットの普及を阻む最大の障壁は「使いやすさ」、それとも「人々のマインドセット」だと思いますか?
マチェイ:むしろマインドセットの問題だと思います。なぜなら、この業界はこれまでオタクっぽい領域として見られてきたからです。多くの人はまず結果からから考え始める傾向があります。つまり、ハードウェアウォレットの管理なんて、とても難しいものだと思われていたわけです。
でも、もうそんな時代じゃない。ユーザーは、エンジニアである必要もないし、技術に関する知識がなくてもいいんです。そして今日ご覧いただいた「Trezor Safe 7」は、まさにそれを証明していると思います。もう触ってみましたか?
── はい、試しました。

 ※「Trezor Safe 7」は、直感的なタッチ操作が可能な2.5インチの高解像度カラーLCDディスプレイを備えた新型モデル。手の平に収まる美しいデバイスは、完全に暗号化されたBluetooth接続でモバイルとも連携でき、Qi2対応ワイヤレス充電にも対応している。セキュリティ面では新開発のセキュアエレメント「TROPIC01」により、透明性と安全性を両立した設計になっている。
※「Trezor Safe 7」は、直感的なタッチ操作が可能な2.5インチの高解像度カラーLCDディスプレイを備えた新型モデル。手の平に収まる美しいデバイスは、完全に暗号化されたBluetooth接続でモバイルとも連携でき、Qi2対応ワイヤレス充電にも対応している。セキュリティ面では新開発のセキュアエレメント「TROPIC01」により、透明性と安全性を両立した設計になっている。マチェイ:ご覧の通り、これらのデバイスは洗練されていて見た目もとても美しい。しかも使いやすい。「ハードウェアウォレットは扱いにくい」なんていうのは、もう過去の話ですから、「難しい作業が必要なんじゃないか」と心配する必要は全くありません。
そして、普及への近道は、セルフカストディは難しくないということをユーザーに教育することだと考えています。
ちなみに、トレザーは教育面での取り組みの一環として、「トレザー・エキスパート(Trezor Expert)」*というサービスを提供しています。そこでは、トレザーのエキスパートと1対1でセッションを予約できます。セッションでは、トレザー製品のあらゆる初期設定をお手伝いし、疑問点にはすべてお答えして、ユーザーをサポートしています。
*トレザーエクスパートはオンラインで提供されるハードウェアウォレットの個人向け導入支援サービス。1対1のビデオ通話でハードウェアウォレットの設定を支援し、全工程を丁寧にガイド。初心者でも安心して暗号資産を安全に管理できるようサポートしている。
マチェイ:そして今、業界全体も成長しています。実際、セルフカストディの必要性はこれまで以上に高まっています。なぜなら、最近はETFのような、ビットコインのように見えるけれど、実際はビットコインではない金融商品がどんどん増えているからです。また、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を第三者のカストディアンに預けるようなケースも増加しています。
しかし、資産を真に所有するという意味では、自ら管理するセルフカストディこそが本質的な形だと私たちは考えています。そのほうが単純に優れていますしね。
なぜオープンに? トレザーが貫く透明性哲学
── トレザーの「Trustless by Design(信頼を前提としない設計)」という理念のもとで、自由とセキュリティのバランスをどのように製品設計やユーザー体験に反映していますか?
マチェイ:私は自由とセキュリティは表裏一体で、この業界では切り離せない関係にあると思っています。むしろ、相互に内在する要素であって、どちらか一方を欠くことはできません。
なぜなら、私たちは個々の自由を守るために安全であることが求められるデバイスを作っているからです。その考え方が私たちの基本姿勢です。そして、その実現のために私たちはできる限り透明性を保つよう努めています。
自由を守るためには、まず信頼を前提にしない設計が必要です。そのため私たちはコードを完全にオープンソース化し、さらに今回、監査可能な専用チップも導入しました。これは業界でも例を見ない取り組みです。これこそが今回のハードウェアにおける最大のイノベーションであり、同時に他社との大きな差別化要因でもあります。
 ※イベントには、トレザーのCTOであるトマーシュ・スサンカ(Tomáš Sušánka)氏も登壇し、ポスト量子暗号に対応したオープンソースのセキュアエレメント「TROPIC01」について、その監査性と技術的特徴を解説した。
※イベントには、トレザーのCTOであるトマーシュ・スサンカ(Tomáš Sušánka)氏も登壇し、ポスト量子暗号に対応したオープンソースのセキュアエレメント「TROPIC01」について、その監査性と技術的特徴を解説した。── たとえば競合他社の製品と比べ、トレザーはハードウェアからソフトウェアまでオープンソース化していますよね。セキュリティの世界では、オープンであることがリスクや妥協を伴うこともあると思いますが、それでもトレザーが透明性と検証可能性を重視するのはなぜでしょうか?
マチェイ:実は、私たちはこれまでに、クローズドソースの専門チップのセキュアエレメントを扱った経験があります。それらは透明性がありません。実際、私たちは競合他社が使用しているのと同じ種類のチップをテストしました。すると、いくつかの脆弱性を見つけたのです。
具体的には、実際に使い始める前の段階で、それらのチップから秘密鍵を抽出できてしまう方法を発見しました。しかし、当時私たちはそれらのチップメーカーとNDA(秘密保持契約)を結んでいたため、その問題を公表することはできませんでした。「脆弱性を発見した」と公に言うことも、市場でまだ同じチップを使っている競合企業に警告することもできなかったのです。
これは明らかなセキュリティ上の問題ですよね。もしハッカーが同じ脆弱性を見つけてしまえば、他社のデバイスを攻撃してユーザーに被害を与える可能性があります。
だからこそ私たちは、監査可能な独自のセキュリティ・エレメントを開発することを決めました。これが監査可能であることが非常に重要であり、オープンソースが不可欠である理由です。


変わりゆく規制環境の中で、自由をどう守るか
── 世界中で規制は急速に進化しています。将来的にハードウェアウォレットにもKYC(本人確認)を義務付ける国が現れる可能性はあると思いますか? もしそうなった場合、トレザーはどのようにコアとなる哲学を貫くのでしょうか?
マチェイ:実を言うと、私自身もその点は少し懸念しています。現時点では、私たちの領域、つまりセルフカストディやハードウェアウォレットに関しては明確な規制はまだ存在していません。言い換えれば、この分野は今、未規制の自由な領域であり、ユーザーはKYCなどの手続きを経ずに、自分の資産を自分で安全に保管できる状態です。
もし将来的に、ハードウェアウォレットの利用にまでKYCが義務づけられるような規制が導入されるとしたら、私は人々の自由が脅かされることを本気で懸念します。なぜなら、お金をどう持ち、どう使うかという自由は、言論や表現の自由と同じくらい重要な人権だからです。人々は政府や企業などの干渉を受けることなく、自由に取引を行う権利を持つべきだと思います。
ですから、もしそうした規制が現実になっても、私たちはどうすればKYCを課さずにセルフカストディを維持できるかという方法を探し続けると思います。
── 人々が自由に生きること、そしてそれを支える創造性を大切にしている姿勢が伝わってきます。少し話題を変えますが、マチェイさんご自身も、音楽というクリエイティブな世界からテクノロジーの領域へと進まれていますよね。その経験は、トレザーでのデザインや創造性の考え方に影響を与えていますか?
マチェイ:そう思います。少し抽象的に聞こえるかもしれませんが、主に、努力のスタイルという面で影響があると思います。つまり、創造性そのものと直接つながっているというよりは、むしろ私がさまざまな芸術分野を学ぶ学校で過ごす中で得た経験と関係しているんです。
私は芸術アカデミー(Academy of Performing Arts)で学んだのですが、映画や演劇、そして純粋芸術アカデミー(Fine Arts Academy)など、幅広い芸術分野の授業を受けていました。
ですから私は世界を、クリエイティブな視点からみると「やろうと思えば何でも実現できる」といった感覚で見るようになったと思います。
一方で、音楽家として学んだ一番のことは、継続と努力です。私は7歳の頃から、ほぼ毎日8時間、20歳くらいになるまでずっと練習していました。平日も週末も、時間があれば常にギターを弾いていました。つまり、技術を磨くためかなり厳しい練習のルーティンを積み重ねていたんです。その中で気づいたのは、「十分な時間と根気さえあれば、どんなことでも実現できる」ということです。
それが、私にとって一番大きな学びです。
歴史が形作ったトレザーの原点
トレザーが掲げる「trustless by design」の背景には、トレザーが拠点を置くチェコの歴史が深く関係している。
マチェイ氏はイベントのオープニングリマークスにて、チェコ人の体制への懐疑心の背景として、1953年に起きた大規模な通貨改革に言及した。
第二次世界大戦後、チェコでは共産党が権力を握り、自由経済は消滅。経済は中央管理下に置かれた。政府は「通貨は安全」と宣言した翌日に突然、新通貨への交換を発表。法定通貨であった旧チェココルナは無効化され、新しい通貨への交換は、現金は1人あたり300コルナまで、5対1の比率でしか交換できず、銀行預金は最大50対1で切り下げられた。
結果として、国民の貯蓄の約90%が一夜にして失われ、皮肉なことに、深刻な打撃を受けたのは富裕層ではなく、政権が守ると宣言していた労働者階級だったという。
マチェイ氏は、この出来事によって「自分のお金をコントロールできなければ、それは本当の意味で自分のものではないという意識は今も私たちの心に深く刻まれている」と語った。
チェコが民主主義を取り戻した1989年のビロード革命のデモで、人々は鍵を鳴らし、自由の回復を告げた。その象徴的な音は、体制への不信と、自らの手で未来を取り戻すという意志の表明であったという。
そして、その20年後、秘密鍵を守ることを使命に掲げ、トレザーは世界初のハードウェアウォレットを世に送り出した。
「歴史は繰り返す。だからこそ、私たちはその教訓を刻み、自らの資産と自由を自らの手で守らなければならない。真の所有とは、自らがコントロールできる状態にあること。そして、私たちはその自由をすべての人へ届ける」。
マチェイ氏の言葉には、誰もが自由を自ら選び取れる世界を守ろうとする、揺るぎない信念が滲んでいた。
Trezor safe7について
次世代ハードウェアウォレット「Trezor Safe 7」は、モバイル接続を強化し、どこからでも暗号資産を安全に管理できるよう設計された最新モデルだ。最大の特徴は、世界初のオープンソースかつ監査可能なセキュアエレメント「TROPIC01」を搭載している点にある。これにより、従来の「ブラックボックス化された独自チップ」への信頼に頼る必要がなくなり、誰でも設計を検証できるオープンな仕組みを実現した。
さらに量子対応アーキテクチャを採用し、ポスト量子時代の暗号更新にも対応。トレザーはSafe 7を、世界初のポスト量子対応ハードウェアウォレットと発表しており、デュアルチップ構成(TROPIC01+EAL6+準拠チップ)によって、防御を強化している。
具体的には、量子対応アーキテクチャと量子セキュリティ対応ファームウェア更新のサポートにより、「Trezor Safe 7」は今後も長期的にその完全性が保証される設計だ。将来的にネットワークがポスト量子セキュリティへ移行しても、ハードウェアウォレットを交換する必要はない。リカバリーキーと組み合わせることで、量子技術や脅威が進化してもユーザーは完全な管理権を維持できる。
秘密鍵はホストシステムから完全に隔離され、すべての機密操作は2.5インチ高解像度カラーLCDタッチスクリーン上で物理的に確認する必要がある。この設計により、ユーザーは各操作を自らの目と手で確認しながら、安全に実行できる。
主要なウォレットアプリ、DeFiプラットフォーム、dApps、NFT ($0.00)マーケットプレイスなどともシームレスに連携可能で、Trezor上で直接、安全に暗号資産の売買・交換・ステーキングを行える。
さらに、「Trezor Safe 7」はモバイル・デスクトップ・タブレットなど、あらゆるデバイスでの管理に対応。オープンソースの暗号化技術によってBluetooth通信は完全に保護され、Qi2対応のワイヤレス充電機能がバッテリーを常に最適な状態に保つ。搭載されるリン酸鉄リチウム電池は、標準的なリチウム電池の約4倍の充電サイクルを実現し、長期保管でも安定した性能を維持できるという。
筆者も実際に「Trezor Safe 7」を体験したが、取引の確認や、端末画面で確認するその他の重要な操作を行う時にデバイスが振動し、触覚的にも操作の確証を得られる安心設計だと感じた。
アプリ「Trezor Suite」からは数千種類のコインやトークンを一元管理でき、本体価格は249ドル。11月23日から販売開始予定で、チャコールブラックとオブシディアン・グリーン、ビットコイン専用モデルが現在予約受付中だ。
Trezorについて
Trezor(トレザー)は、2013年にチェコ・プラハで設立された、世界初のビットコインハードウェアウォレットのパイオニア企業。暗号資産を「自分で保管する(セルフカストディ)」という概念をいち早く提唱し、オープンソース技術を通じて、個人が中央機関に依存せずに暗号資産を安全に管理できる環境を提供してきた。
トレザーは、創業以来すべてのハードウェアおよびソフトウェアを完全オープンソースとして公開しており、その透明性は暗号資産業界におけるセキュリティの新しい標準を確立した。
現在では、初心者から上級者まで幅広いユーザーを対象に、暗号資産の安全な保管・運用を支える多層的な製品群を展開している。
また、トレザーはユーザーデータを一切収集しないという厳格な方針を貫いている。ユーザーアカウントやデバイスIDなどの識別情報を保持せず、「トレザー・スイート(Trezor Suite)」で提供される分析機能も、ユーザーが接続を解除した時点で完全に終了する仕組みだ。ログインを再開しても情報は引き継がれず、継続的なトラッキングは一切行われない。取得されるデータはすべて集約・匿名化されたものであり、プライバシー保護への徹底した姿勢が同社の哲学に深く根付いている。
2023年には、暗号資産エコシステムへの安全な参加を促進する教育プログラム「Trezor Academy」を開始。草の根的なコミュニティ教育を通じて、暗号資産のリテラシー向上とセルフカストディの普及に力を入れている。
トレザーは、ビットコインおよび暗号資産分野の革新に注力するテクノロジー持株会社SatoshiLabs(サトシラボ)の一員であり、その理念は、「Don’t trust, verify(信頼するな、検証せよ)」というビットコインの精神を体現している。
関連リンク
- 「Trezor Safe 7」公式ストア
- Trezor Expert
- Trezor TBD—Trustless by Design—
インタビューイ・プロフィール
マチェイ・ザーク(Matej Zak)
Trezor CEO
マチェイ・ザーク氏は、2019年の入社以来、プロダクトイノベーション、ユーザー体験、グローバル市場展開において中心的な役割を果たし、2023年にCEOへ就任。現在は「ビットコインをより多くの人々に安全に届ける」というビジョンのもと、業界最高水準のセキュリティとプライバシーを維持しながら、Trezorの事業戦略を牽引している。プロダクトマネジメント、ビジネス開発、コンシューマーテクノロジー領域の国際展開など幅広い経歴を持つ。また、音楽分野のバックグラウンドを持つ経営者でもあり、Berklee College of MusicでGlobal Entertainment & Music Businessの修士号を取得している。
取材/編集/撮影:髙橋知里(あたらしい経済)











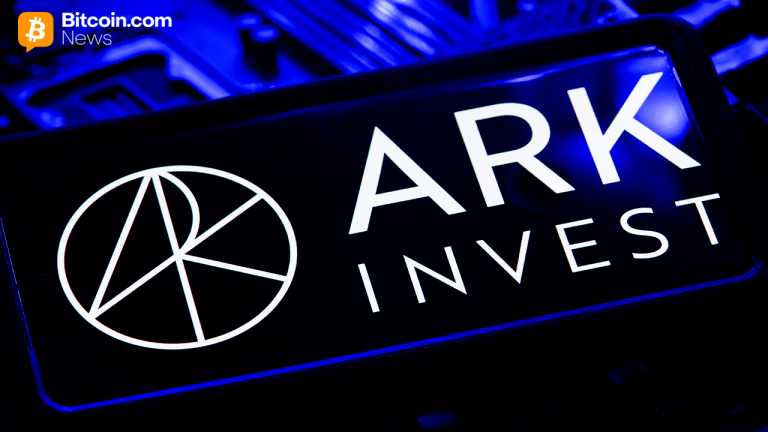


 24h Most Popular
24h Most Popular








 Utilities
Utilities