
有識者らと課題・論点整理へ
金融庁が、金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ(WG)」の第2回会合を9月2日に開催。委員や専門家らは、暗号資産(仮想通貨)の規制を資金決済法から金融商品取引法(金商法)へと移行する方向性について議論した。
事務局資料によると国内の暗号資産市場では、口座開設数が延べ1,200万口座を超え、利用者預託残高は5兆円規模に拡大したという。一方で、口座資産額の8割以上が10万円未満と小口投資が中心であり、利用者の7割が年収700万円未満の中間所得層で、長期的な値上がりを期待した投資行動が目立つと報告された。
会合では、暗号資産を投資商品として位置づける動きが世界的に広がる中で、国内制度の見直しの必要性が改めて指摘された。米国ではビットコイン現物ETFが上場し、欧州では市場操作やインサイダー取引規制の整備が進むなど、国際的なルール整備が加速していることも報告された。
事務局説明資料では、「発行者による情報開示の充実」・「無登録業者への実効的エンフォースメント」・「価格形成・取引の公正性確保」・「サイバーリスクを踏まえた顧客資産の安全管理」などが論点として示された。
さらに金融庁は、暗号資産を「資金調達・事業活動型(類型①)」と「それ以外(類型②)」に分類し、情報開示や事業者規制を適切に設計する方向性を提示。
資金調達・事業活動型トークン(類型①)については、発行者に対する情報開示義務を強化する。一方でビットコインやイーサリアムなど発行者が存在しない非資金調達型トークン(類型②)については、交換業者による情報提供義務を課す案が示されている。なお、留意点として、分散化の進行により資産の性質が類型①から②へ移行する可能性も念頭に置いて整理するとされた。
金融庁はトークン分類の基本的な考え方として、類型①を「資金調達の手段として発行され、その調達資金がプロジェクト・イベント・コミュニティ活動等に利用されるもの」、類型②を「類型①に該当しないもの」としている。
これについて日本ブロックチェーン協会(JBA)はヒアリング資料で、類型①の分類方法として、「実質的な生成等の意思決定権をもつ特定の者ら」における「議決権51%以上の保有」と「オフチェーン(取締役会・契約等)での意思決定による実質的支配」で評価すべきと提案。
特に新規発行(プライマリー)だけでなく、セカンダリーにおける金庫暗号資産の売却(エスクロー解除を含む)も規制対象として整理すべきとの見解を示した。
また金融庁は、暗号資産の取引を巡る利用者保護強化の一環として、現行の資金決済法に基づく交換業規制を、厳格な枠組みに移行する方向性を示した。急速な市場拡大や詐欺的勧誘の増加を受け、無登録業者への取り締まりや、投資助言・運用行為の規制範囲拡大を検討するとのこと。また技術革新のスピードを踏まえ、柔軟な自主規制との組み合わせや、普遍性の高い規制については法令レベルに引き上げることの検討、顧客資産の安全管理・サイバーリスク対策の徹底を求めていく方針を示した。
また、市場開設規制面では、現行制度下で暗号資産の板取引を行う交換業者が増加しているが、取引所の価格形成機能は限定的であるとして、金融商品取引所の免許制のような厳格な市場開設規制は現時点では必要ないとの見解も示された。
また会合では、業界団体から暗号資産市場の現状について説明が行われた後、各委員による討議が行われた。
その中で、京都大学の岩下直行教授(元日本銀行金融研究所)は、国内のIEOの多くが公募価格を大きく下回り、中には90%以上下落した例もあると指摘。
岩下教授は、こういった商品を一般投資家向けの金商法の枠組みに取り込むことについては慎重に検討すべきとの姿勢を見せている。
金融庁は今後、利用者保護とイノベーションの両立を図りつつ制度設計を検討し、WGでの議論を継続する方針だ。
参考:発表
画像:iStock/ pgraphis・Rawpixel
関連ニュース
- 金融庁、「暗号資産・イノベーション課」設置を要求
- 金融庁、暗号資産の「取引課税見直し」と「ETF組成検討」を正式要望、26年度税制改正で
- 金融庁、政府へ暗号資産取引の分離課税を要望=日経
- JVCEAとJCBAが金融庁に要望書提出、暗号資産の2026年度税制改正に向け
- 金融庁、暗号資産を2類型に分けた規制検討を提案









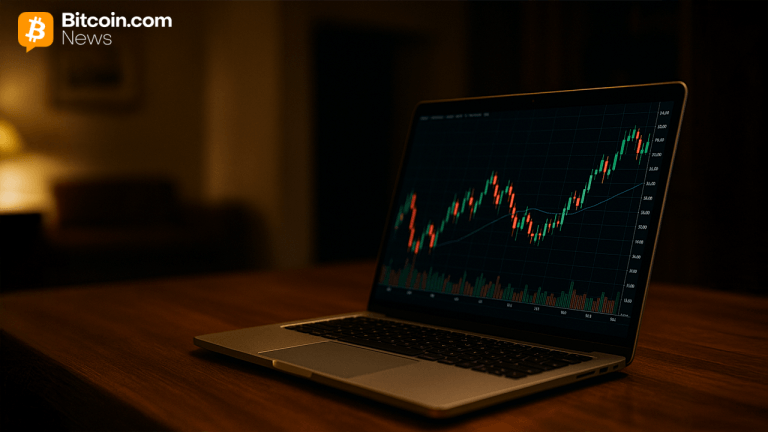








 24h Most Popular
24h Most Popular

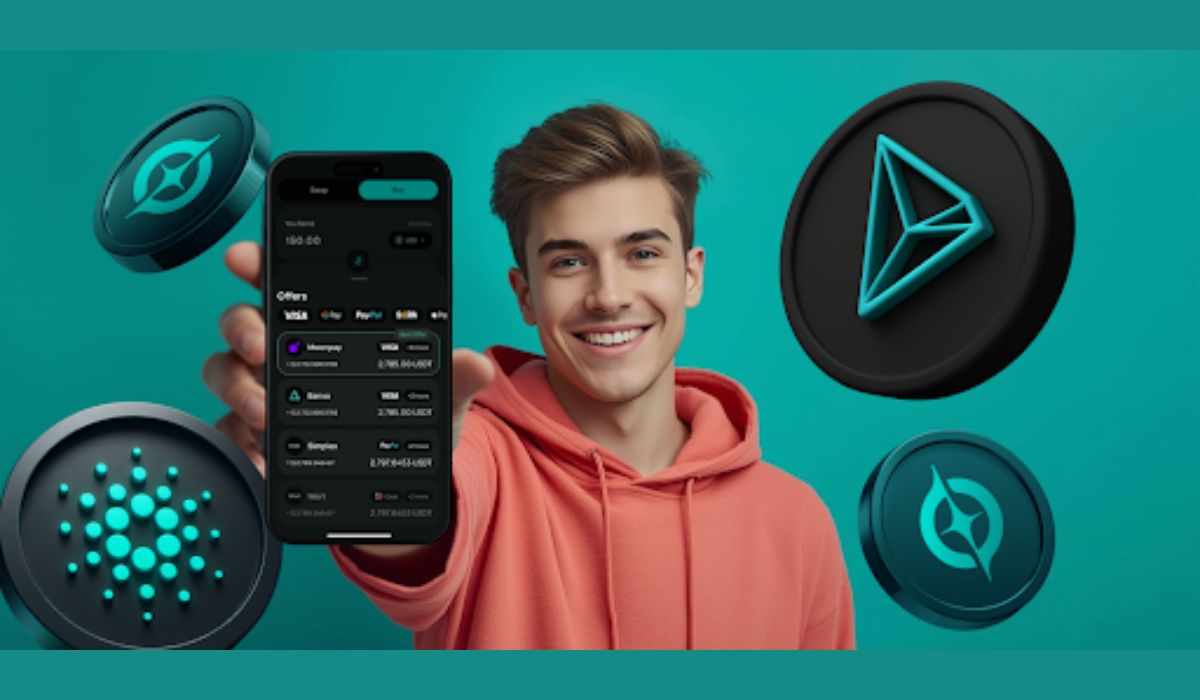





 Utilities
Utilities