
レンディングを金商法の規制対象と位置づけ
金融庁が、金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ(WG)」第5回会合を11月7日に開催し、暗号資産(仮想通貨)のレンディング事業への規制強化や、ICO・IEO(取引所による暗号資産販売)を巡る課題について議論した。
今回の議論では、これまで資金決済法で扱われてきた暗号資産レンディング類型を、金融商品取引法(金商法)に取り込む案が示された。
金融庁が発表した資料では、利用者から暗号資産を預かり利回りを付与するスキームを、「リターンを追求すると言う意味で、投機的な性質を有する」と評価し、その前提で金商法での規律を提案した。暗号資産借入に関連する信用リスク低減の観点から、再貸付先の破綻リスクやステーキング委託先のスラッシングなどに関するリスク管理体制の整備を求めることに、行為規制を課すことが提案された。
これにより、暗号資産を貸し出して利回りを得る行為は、有価証券の募集・販売や投資運用と同等の情報開示・説明義務が課される可能性がある。
また、貸付・預かり・再貸付といった、貸し付けに類するスキーム全般を対象に、金融商品取引業の一種として監督する案が検討されている。
また金融庁は、暗号資産の監督体系を資金決済法から、金商法に移す方向性も示した。
従来は、決済・交換手段として規定されていた暗号資産だが、今や市場の大半が投資目的の取引となっている。金融庁は「多くの暗号資産取引が価格変動による利益を目的としており、金商法の理念と整合的」と明記している。
これにより、暗号資産を「株式や債券とは別の新しい規制対象」として金商法上に位置づける案が浮上した。
同時に、暗号資産交換業に課してきた、分別管理、情報提供、広告規制などの規制を金商法内に再構築し、資金決済法上の暗号資産規制を削除する案も提示された。
なお、金商法で規制することになっても、決済目的での利用が制限されるものではないとされた。規制見直しによって利用者保護のための規制やエンフォースメントが強化されることは、決済目的の利用者にとっても、より安心して取引を行うための環境整備になると金融庁は考えている。
また、金融庁は今回の資料で、暗号資産関連企業のICOやIEOに関しても課題整理を行った。
これまでに、発行体が事業計画を実現できず上場後に価格が大幅下落したIEO案件などが確認されていることを背景に、今後は以下のような対応を進める方針だ。
まずは発行体に対する情報提供体制の強化だ。虚偽記載や誤った情報提供に対する民事責任規定を設け、透明性を高める。
また、暗号資産交換業者に対し、審査部門の独立性・専門性を強化し、取扱う暗号資産の審査体制を一層厳格化するとした。
さらに、審査の中立性を担保するため、法定委員会や独立組織の設置を求め、自主規制機関のガバナンス強化も促している。
そして、顧客適合性の確認強化や、投資家への説明責任の拡充による投資者保護の徹底も求めた。
さらに、複数の暗号資産交換業者が関与するIEOにおける価格変動リスク、発行体やチェーン変更時の対応、適時開示の明確化など、自主規制機関においてIEOの以下の諸課題を踏まえた対応を検討・実施することも提案されている。
なお、金融庁は今回の規制見直しにあたって、「規制を見直すことは暗号資産投資についてお墨付きを与えるものではない」との立場を示し、投資者が暗号資産のリスクや商品性を十分に理解し、リスクを許容できる範囲で投資を行うことはあり得るとの前提で、健全な取引環境を整備すべきとした。
また、日本における健全なイノベーションの可能性を後押しすることも大切だとしている。
参考:発表
画像:PIXTA
関連ニュース
- 片山さつき財務相、金融庁の3メガバンク共同ステーブルコイン発行支援を表明
- 【追記】金融庁、3メガバンクらのステーブルコイン共同発行の実証実験を支援決定
- 金融庁、海外の暗号資産ETF原資産のデリバティブ取引に「望ましくない」との見解
- 金融庁、無登録暗号資産取引所を宣伝するXアカウントへ注意喚起を実施
- 金融庁、銀行が暗号資産の投資・交換業登録を可能にする制度改正検討か=報道











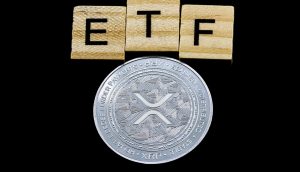



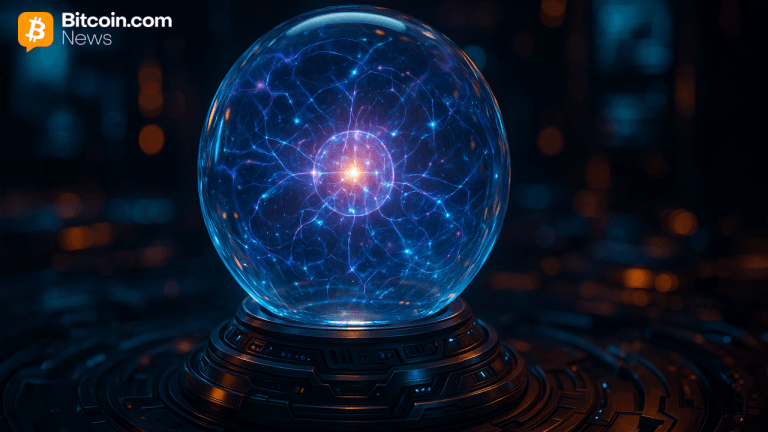

 24h Most Popular
24h Most Popular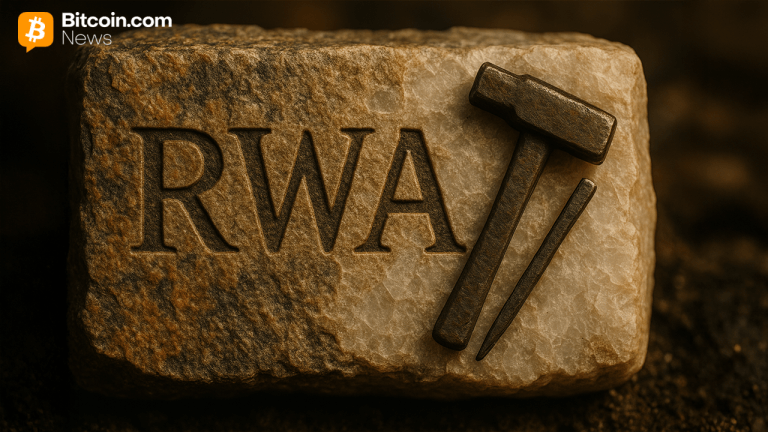








 Utilities
Utilities