
交換業取扱の暗号資産105銘柄が「金融商品」の対象に
金融庁が、国内暗号資産(仮想通貨)取引所が取り扱う105銘柄の暗号資産について、金融商品取引法を適用し、金融商品として位置付ける方針を固めたと「朝日新聞」が11月16日に報じた。
報道によると同105銘柄の情報開示を交換業者へ義務付けするとのこと。併せて株取引と同様の税率軽減も要望するという。
ただし分離課税の対象となるのは、同105銘柄に限るようだ。業界団体は全ての暗号資産を金融商品として認めるよう求めているという。これについては与党税制調査会が12月に検討するとのこと。
なお報道では、「国内の交換業者は現在、ビットコインやイーサリアムなど105銘柄の暗号資産を取り扱う」とあるが、日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)が公開する情報によると現在国内の交換業者が取り扱う暗号資産の数は119銘柄となる。
同法改正案の提出は2026年の通常国会を目指しているとのことだ。
資金調達目的の暗号資産発行者に情報開示義務付けも
また今回の報道と同日、資金調達目的で暗号資産を発行する事業者に年1回の情報開示を金融庁が義務付けると「日経新聞」が報じている。
対象となるのは、直近の事業内容や将来の発行計画など。投資家が不測の損失をこうむるリスクを減らすのが目的だという。金融審議会の作業部会で詳細を詰め、2026年の通常国会で改正案として提出する意向のようだ。
金融庁は今年4月、「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」の結果をまとめたディスカッション・ペーパーを公表。
その中で金融庁は、規制見直しを検討する際に、暗号資産を機能や性質で区分し、「類型①:資金調達・事業活動型」と「類型②:非資金調達・非事業活動型」の2種類に分類して検討することが適当ではないかと提案している。
「類型①:資金調達・事業活動型暗号資産」は、ICOやトークンセールなど、資金調達の手段として発行される暗号資産だ。調達された資金は、主に特定のプロジェクトやイベント、コミュニティ運営などの事業活動に活用されることが想定される。例として、一部のユーティリティトークンがこれに該当する。
一方、「類型②:非資金調達・非事業活動型暗号資産」は、資金調達を目的としない暗号資産であり、発行者が存在しないか、存在しても事業資金の調達とは無関係なケースを指す。代表的な例として、ビットコインやイーサリアムなどが挙げられている。
参考:朝日新聞・JVCEA・日経新聞
画像:PIXTA
関連ニュース
- 金融庁、暗号資産を金融商品とする改正案を26年に国会提出の方針か=報道
- 金融庁、暗号資産を有価証券と並ぶ金融商品に検討。ETF解禁も視野か=報道
- 金融庁、暗号資産管理システム業者への届出制度の導入検討=報道
- 金融庁、暗号資産レンディング規制強化を議論。ICO・IEOの課題も整理へ
- 金融庁、3メガバンクらのステーブルコイン共同発行の実証実験を支援決定









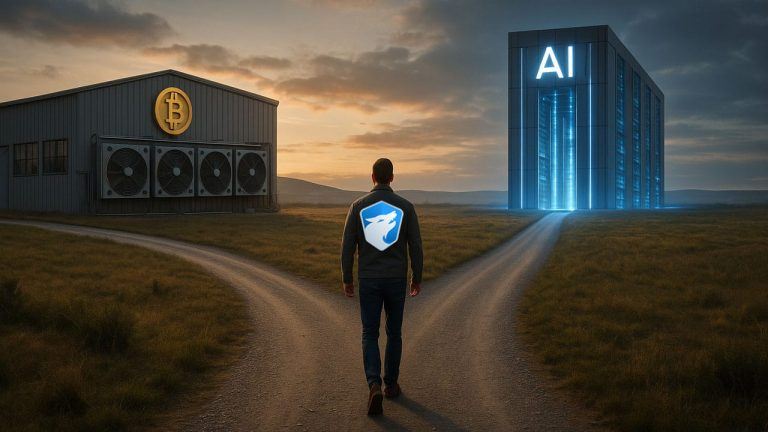








 24h Most Popular
24h Most Popular









 Utilities
Utilities